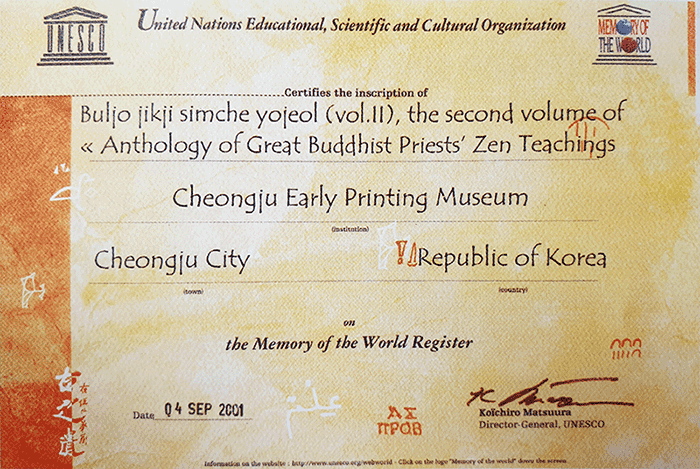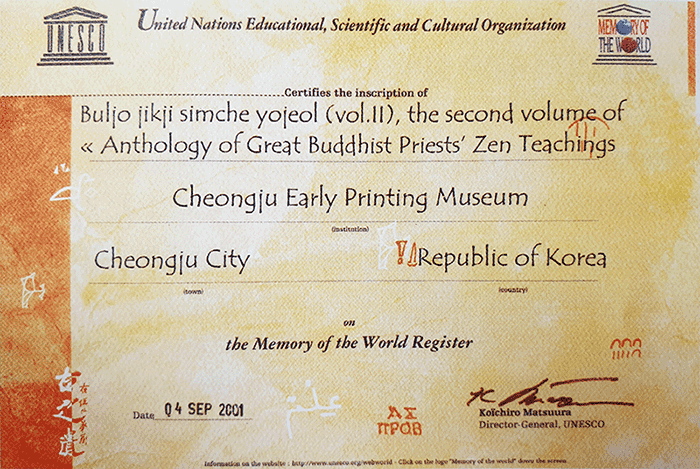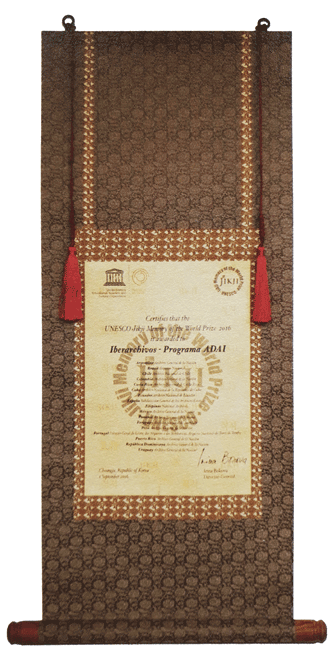ユネスコ直指賞
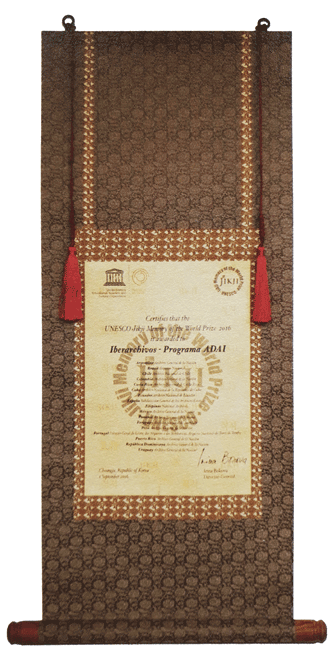
ユネスコ直指賞(UNESCO/JIKJI Memory of the World Prize)
ユネスコ直指賞は、ユネスコが世界記録文化遺産の保護に貢献した人に授与するために2004年に制定した賞である。賞の名前は、現存する世界最古の金属活字本である『直指心体要節』にちなんだものである。
ユネスコ直指賞制定の意味
『直指』が2001年に世界の記録(世界記録遺産)として登載され、2004年4月にユネスコにて[直指賞]が制定されたことにより、その価値が世界的にさらに確固なものとなった。特に世界の記録(世界記録遺産)では初めての賞であり、地方自治団体で制定した唯一の賞として清州の価値が共に高まった。
推進の背景
現存する世界最古の金属活字本『直指』の貴重な価値、すなわち金属活字を発明した創造的価値、世界最高の歴史的価値、知識情報の共有・拡散の価値、芸術・文化的価値と私たち民族の優れた能力を世界に知らせ、韓国と清州が世界の知識情報文化の活動中心地として飛躍することができるということをもう一度浮き彫りにしようと直指賞の制定を推進する。
推進過程
- 2002. 4月外交部、ユネスコ韓国委員会と直指賞制定推進に関連する懇談会
- 2003. 2月直指賞推進計画を提出(清州市→外交部)、直指賞の条例制定後に直指賞の推進を要請
- 2003. 3月直指賞制定建議文(清州市議会→外交部)
- 2003. 5月清州市、直指賞条例(案)を立てる
- 2003. 9月清州市、直指賞条例を公布
- 2003. 9月直指賞を提案(外交部→ユネスコ本部)、ユネスコ第167次執行委員会開催時に提案
- 2004. 4月28日直指賞の制定決定(ユネスコ本部/フランス)、ユネスコ第169次執行委員会で審議・決定
- 2004. 6~8月直指賞の授賞についての協議(ユネスコ本部)
- 2004. 9~11月授賞金および付帯費用を2005年度の予算に反映
- 2005. 6~8月直指賞の受賞者を選定(ユネスコ本部)
- 2005. 9月第1回直指賞授賞式を開催(直指の日/直指祭り)
直指賞の受賞資格と授賞式
- 受賞候補の条件は、人類の記録文化の保存と接近に大きく貢献した個人や団体とし、受賞時期は2005年から2年おきに、清州市直指の日に授賞し、清州市が3万ドルの賞金を支援する。
- 第1回直指賞の授賞は清州市で開催され、開催地はユネスコ本部と協議して決定される。
直指賞受賞機関および団体
第10回受賞機関(2024): インドネシア国立図書館(National Library of the Republic of Indonesia)
1980年に設立されたインドネシア国立図書館は、インドネシアの伝統的な筆写本の古代性と多様性を示すインドネシアの文献を保存してきた。インドネシア国立図書館はこれまで様々な地域や言語、文化を対象にした包括的なプログラムの運営をはじめ、関連分野のフェスティバルや出版物、子供と青少年向けの教育プログラムなどを開発した。特に、主体性を持って文献の収集と保存に取り組むことで、文献へのアクセシビリティの向上に大きく貢献し、様々な事業計画と出版物を通じて国民の認識を高めるべく努めている。


第9回受賞機関(2022) : エジプトのカイロ・アメリカン大学図書館(Libraries and Learning Technologies, American University in Cairo, Egypt)
1919年に開館した図書館で、貴重書・特殊コレクション専門図書館(Rare Books and Special Collections Libraries)を運営し、建築関連コレクションのほか社会・女性史、文化芸術関連記録物など多方面にわたるエジプトの記録物や遺物を収集・保存している。アラブ圏における関連分野の研究ハブを構築して世界中の関連記録物へのアクセシビリティを高めており、記録遺産保存の重要性に対する意識を高める取り組みを通して地域社会に貢献した。

第8回受賞機関(2020) : カンボジア トゥール・スレン虐殺博物館(Tuol Sleng Genocide Museum)
1979年に開館したトゥール・スレン虐殺博物館は元は高校であったが、クメール政権当時に反体制派を拘禁、拷問し虐殺する場所として使われた。残虐だった当時の状況を生々しく伝える記録は、世界的な重要性と固有性を認められ、2009年ユネスコ世界の記録(世界記録遺産)として搭載された。2018年アーカイブ復元およびデジタル化事業により75万枚の所蔵資料を保存処理し、50万枚に達する試料をデジタル化して全世界に提供することにより、未来の世代の正しい歴史の認識と人権平和に対する意識を高めることに寄与している。

第7回受賞機関(2018) : アフリカマリNGO団体サバマ-ディ(SAVAMA-DCI of Mali)
1996年に設立されたサバマ-ディ(SAVAMA-DCI)はアフリカのイスラム文書の保全関連活動を行う非政府機構で、アルカイダ関連武装団体に掌握されたアフリカのマリ北部地域にある多くの遺跡と文書が毀損され得る状況で、マリの「アル-ワンガリ図書館」などに所蔵された文書約600件をデジタル化するなど、古文書を守り保存した功労が認められた。

第6回受賞機関(2016) : Iberarchivos – ADAI Programme
イベルアーカイブは、中南米国家の記録遺産についての接近・保存・拡散・促進のために1999年に設立された。スペイン語およびポルトガル語の使用国家のためのアーカイブ管理研修過程および国家間の共同事業などを推進しており、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、スペインなど合計15ヶ国の国家記録院が参加している。

第5回受賞機関(2013) : メキシコアダビ(ADABI of Mexico)記録保管所
2003年に設立されたメキシコのアダビは、古文書の保存およびデジタル化に寄与し、各種団体の記録保管を積極的に支援して、一般の人たちが文書遺産の重要性を認知するよう努力した。

第4回受賞機関(2011) : オーストラリア国家記録院(National Archive of Australia)
オーストラリア政府の傘下機構として1960年に設立されたオーストラリア国家記録院は、記録保存に関する業界の世界的なリーダーであり、デジタル保存分野を先導する機関である。膨大な出版物で専門的なノウハウを大衆に提供するなど、世界の保存共同体と共有した。

第3回受賞機関(2009) : マレーシア国家記録院(National Archive of Malaysia)
マレーシア国家記録院は、1875年からセランゴール(Selangor)州事務総長の記録を収集・整理・保存し、洪水・火災などの自然災害から記録物を保存および復旧することに寄与した。手紙、日記、写真など民間記録を収集して原型に近く保存することにより、アジア地域の記録保存のたの教育訓練プログラムにも寄与した。

第2回受賞機関(2007) : オーストリア音声記録保管所(The Austrian Audiovisual Reserch Archive)
1899年に設立された世界最高のオーストリア音声記録保管所は、オーストリアだけではなくアフリカ地域の言語、音楽、口伝記録など約6万5千件の音声や映像記録を保有している。オーディオ資料だけを抽出して保管する方式を導入するなど、オーディオ資料保管技術の発達にも大きく寄与した。

第1回受賞機関(2005) : チェコ国立図書館(National Library of the Czech Republic)
1360年に設立されたチェコ国立図書館は600万冊以上の本を保有しており、チェコだけではなく世界の多くの文化を理解する重要な資料を所蔵している。酸性化した紙の図書と文書をCDにして安全に保管し、大衆が接しやすいようにするなど、記録遺産の保存に大きく寄与した。